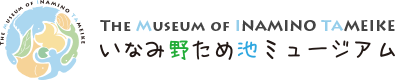加古大溝|詳細
水路の基本情報
名前
加古大溝(かこおおみぞ)
水路の長さ
約4km
水はどこからどこへ
草谷川から取水し、加古大池へ送水します。
水路のお得情報
水路の歴史や伝説
新しい水源をもたない加古新村 (地域)では、印南野台地の旧来の村々が持つ水利権に割り込まなければなりませんでした。そこで既存の余り水を加古大池に導水して、新田開発を行うという方法がとられました。
加古新村では、水田面積の増加に伴い、新田開発の前提となった風呂谷池流(用水)を水源とするかんがい用水が不足するようになりました。
そこで草谷川の非かんがい期の流水を、加古大池に導水することが考えられました。草谷川(流長11,474m・流域14.6㎢)は、雄岡山・雌岡山を源とし、印南野台地を西流し、加古川本流に注ぐ小河川です。しかし印南野台地の主要河川の1つであり、沿岸地域の重要な水源となっていました。
大溝用水は、延宝8(1680)年6月に草谷川を水源とする新規用水として、草谷川関係村が、加古新村(国岡新村を含む)の非かんがい期の取水を承諾され、加古新村が草谷川の上流に堰を設けて分水し、さらに加古大池まで約4kmもの承水溝を建設しました。この承水溝が今日の加古大溝です。
なお大溝用水は加古新村と同様、水源の不足に悩まされていた国岡新村と共同で開発されたものであり、五軒屋水分所において、加古新村 7対、国新村3の割合で分水されています。
大溝用水の完成は、加古新村の用水問題を著しく好転させましたが、非かんがい期の引水方法にもいくつかの問題があり、用水路の性格からも水漏れがかなりありました。
そこで、宝永7(1710)年、大溝用水補強の目的で、大溝用水取入口の上流数百mの地点の広谷村用水源「河原田井堰」の余水を直接大溝用水に流入させることが、広谷村に認められました。
今日の草谷川における水利秩序は、大溝用水の水利開発をはじめ、後発村と先発村との水利調整のなかで順次形成されてきたものです。
(出典 兵庫県加古土地改良区誌 平成7年:兵庫県加古土地改良区)
近くのトイレ
・加古大池管理棟
・加古大池ふれあい広場
・淡山疏水・東播用水博物館
近くのお店
コンビニ:ローソンの稲美野谷店
近くの訪問先
・加古大池
・五軒屋分水所
・くそたれ坂
・分境石(明石領・姫路領)
・練部屋分水所
・野寺山高薗寺鬼追式(民俗文化財) 2月10日
・淡山疏水・東播用水博物館
・稲美町立郷土資料館
・播州葡萄園歴史の館
守る
管理者連絡先
兵庫県加古土地改良区 TEL:079-492-4500
農家のため池保全活動、日常管理、安全対策、指定管理者
日常点検、草刈、防災パトロール、施設日常管理
非農家の関わり
清掃活動、みぞさらえ
参加型の情報投稿、関連団体HPとリンク