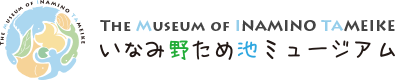練部屋分水所(ねりべやぶんすいじょ)
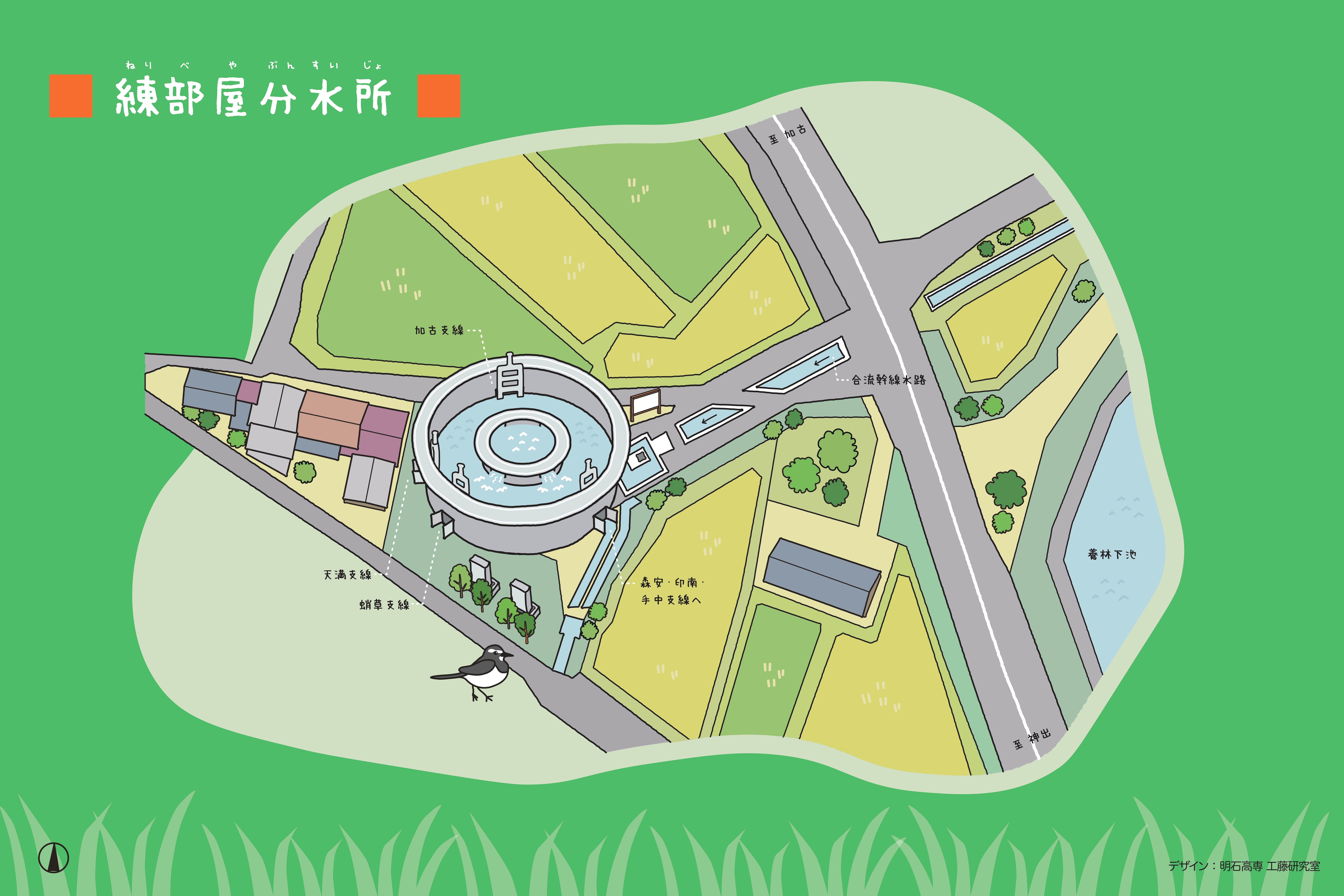
練部屋分水所(ねりべやぶんすいじょ)
練部屋分水所は、水源の淡河川と山田川から水路により導かれた用水を、下流の六つの地域(加古、天満、蛸草、森安、手中、印南)に分水する施設です。
1891(明治24)年に造られましたが、1959(昭和34)年に兵庫県の農業水利改良事業で、より正確な分水が可能な鉄筋コンクリート製の円筒形に改修され現在の姿(円筒分水工)となりました。
現在の施設は、配水口は統合されて、四つとなっています。
分水所は、上流から流れてきた水が一旦その下部に潜り中央から吹き上げ、水の流れと水位を安定させて水を分ける複雑な構造をした施設です。
練部屋分水所に見る分水の仕組みは、大正3年に岐阜県技師により科学的な流量分水方法として考案された円筒分水(当時は放射式分水装置と呼ばれていました。)に先駆けた合理的な分水を可能とする当時の最先端の施設であったと評価でき、全国的に見ても希少な事例です。