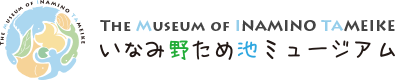風呂ノ谷池(ふろのたにいけ)

風呂ノ谷池(ふろのたにいけ)
3つの重ね池
風呂ノ谷池は、その下流に風呂ノ谷中池、さらに風呂ノ谷下池の3つの池が連なっている。このように棚状に複数の池が連なっている池を「重ね池」と呼びます。
築造された時代
風呂ノ谷池が築造された時代は不明であるが、稲美町史には風呂ノ谷池へ水を引いていた「四百間溝(しひゃっけんみぞ)」と呼ばれる水路が万治元年(1658年)には開発されていたと記載があることから、少なくとも360年以上前には存在していました。
なお、この四百間溝は延長3kmにわたり、水源は練部屋の西北西約500mにある吉生村(神戸市西区神出)の井戸でした。この水路はほ場整備によって、その痕跡はなくなっています。
加古大池のとの関わり
加古大池が造成された万治4年(1660年)、その水源は風呂ノ谷池流で、風呂ノ谷池の水が十分溜まれば、加古大池へ繋がる流溝(水路)に水を流すというものでした。すなわち、風呂ノ谷池の余った水を加古大池へ流していたということになります。
様々な機能
○歴史
風呂ノ谷池の池底には「風呂ノ谷池遺跡」という新石器時代の遺構があり、ナイフ型の石器が見つかっています。
○生態系保全
平成29年(2017年)からコウノトリがため池に飛来したことをきっかけに、平成30年(2018年)にコウノトリの生息しやすい環境を整えるために餌場となる浅瀬を造成しました。これは、秋から冬にため池の水を抜く「かいぼり」をしたときにでも、浅瀬として水が残る場所をつくり、魚の住みかやコウノトリなどの鳥の餌場となります。
さらに令和2年(2020年)には、コウノトリが営巣・繁殖することを願って、風呂ノ谷下池の近くに人口の巣棟を設置しました。
○洪水調整
大雨が降った時に雨水を一時的に貯留する機能を有しています。ため池下流の農地や家屋への洪水被害を軽減する効果があります。
大規模改修工事
加古大池が造成
平成27年度~令和元年度にかけて、老朽化が進んでいた風呂ノ谷池と風呂ノ谷下池の改修工事を行いました。改修工事では、堤体や取水施設、洪水吐を新しくするとともに、耐震性や防災機能が向上しました。